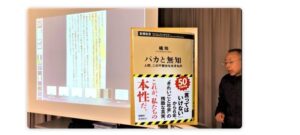心理機制
旧フォーラム≪ブラインド・マインドと失感情症の違いは何?…≫
ALEXは元来、心療内科系の現場でもっとも診断され、運用される概念なので、身体症状症、依存症、適応障害、うつ病などと関連付けられて語られることが多いわけですが、痛みの臨床にあっては、その対応のむつかしさという観点から非常に重要な因子のひとつになっています。
CRPS(RSD)をはじめとする難治性疼痛はもちろん、その他のありふれた運動器疾患(とくに今回の講義で取り上げた四十肩には多く潜在する)にも、ALEXがけっこうな頻度で隠れています。
動画ページ【定期セミナー講演】「認知的柔軟性とは何か?」①~②全40分
養老孟司氏が自著の中で語っていた“壁”は当会が唱える“ソフト認知の壁”と同質のものであり、今日における日本人の認知的柔軟性の問題を見事なまでに予言していた。
認知的柔軟性を考える上で欠かせないメタ認知は実は個人のウェルビーングのみならず人生そのものを決定づける極めて重要な能力。本動画ではメタ認知を7種類に分けて解説した上で、認知的柔軟性を構成する必須9因子について解説。
動画ページ【定期セミナー講演】「認知科学とメタ認知~ダニング・クルーガー効果~」①~②全35分
2022年橘玲氏の「バカと無知」がベストセラーに。実際の中身は「認知科学入門」とも言うべきもの。認知的柔軟性の維持に欠かせないメタ認知(とくに能否メタ認知)を考える上で必須のダニング・クルーガー効果。ハード論偏重の医学界は自らの認知的柔軟性をメタ認知してソフトとハードの統合に向けて歩みを。人間の本質は構造的な次元(ハードの集積体)のみで成立しないわけで。多くの医療者はダニング・クルーガー効果は自分たちとは無関係だと思っているが様々な職業人のなかでも実は…(続きは本動画の中で解説)。
動画ページ【定期セミナー講演】「認知科学とミスリード~ファスト思考&スロー思考~」全18分
画像ラベリングに象徴されるハード論のほとんどは、認知科学を一切考慮せず、さらにファスト思考によるロジックエラーを生み出す。医療ミスリードの背景にファスト思考やダニング・クルーガー効果がある。認知科学と経済学を統合した心理学者ダニエル・カーネマンはヒューリスティックをファスト思考、アルゴリズムをスロー思考と呼んだ。当会は『認知科学と医療を統合した「認知科学統合療法」や「痛み記憶の再生理論」等で有名。構造的な痛みをハードペイン、脳システム由来の痛みをソフトペインと呼ぶことで、医学界に認知科学の重要性を知らしめた。
動画ページ【定期セミナー講演】「アダルトクライングの感謝仮説」①~②全38分
アダルトクライングにおける泣きの個人間機能(人前での泣き行為)、泣きの個人内機能(独りでの泣き行為)、心理的側面と生理学的側面の研究報告を総覧し、「感謝で思考は現実化する」という著作ならびに量子生物学の知見を引用しつつアダルトクライングに秘められし脳弾塑性の発現について。傾聴カウンセリングの現場では泣きという感情解放が痛みの改善に繋がるケースと繋がらないケースが。泣いて良くなる人、泣いても良くならない人、この違いは何に由来するものなのか?詳しく解説。
クラムジーとイップスとオスグッド~認知科学統合の視点~
クラムジーは成長期に発生する運動回路エラーであり、イップスは成長期に限らず全世代で発生し得る運動回路エラーであり、オスグッド氏病(以下オスグッドと略す)は成長期に起きやすい運動回路エラーに伴う膝下(脛骨結節付近)の痛み。クラムジーとオスグッドは、成長期特有の問題として、筋骨格系の急激な成長(ハードの拡張)に脳の神経応答(ソフトのアップデート)が追いつかず、運動覚の失調(パフォーマンスの低下)や痛みなどを引き起こす。
動画ページ【定期セミナー講演】「外科手術後の術創部に対するタッチング〜ルーチン化することの意義〜」10分
概要 外科手術は腹腔鏡下に象徴されるように、より低侵襲なアプローチがトレンドになっています。同時に術後の入院日数も総じて短縮傾向にあるわけですが、しかし術創部に対する看護ケアにはまだまだ改善の余地が残されています。そ […]
動画ページ【定期セミナー講演】「取り外し可能なテーピング軟性固定~突き指バージョン~」12分
概要 外傷管理において、患者の通院頻度は非常に重要です。しかし、全ての患者が医療者の思惑通りに通院してくれるとは限りません。なかには初診の1ヶ月後にひょっこり現れたりするケースがあります。 事前にそういう事態が予想さ […]
動画ページ【定期セミナー講演】「採血によるパニック発作が「正中神経損傷後のCRPS(RSD)」と誤診された症例〜アナフィラキシー鑑別&アドレナリンとノルアドレナリンの違い~」①~②全37分
採血時の針刺し事故に関しては、いわゆる本物と偽物があり、後者の場合、実際には神経損傷には至っておらず、痛みの正体はソフトペインであるケースがほとんど。パニック発作あるいはこれに準ずる脳の誤作動によってソフトペインが生じ得るメカニズムを知っていて、かつ心身統合の臨床経験値を持つ医療者であれば、誤診のリスクは最小限に抑えられるが、ハード論の現場ではそうしたリスクが常に潜在している。「痛み=ハードペイン」という固定観念および先入観が、いかに危ういものであるか…。筆者は整形勤務時代、子供の橈骨骨折の治療に際し「ボキッ」という整復音を聴いた母親が、自分の腕に痛みを感じたという事例を経験。皮膚兎錯覚(cutaneous rabbit)やラバーハンド・イリュージョンの実験で証明されているように感覚の転移は現実にある。とくに共感力の高い人(エンパス)では、こうした幻の痛みを感じてしまう現象が起きやすく、傾聴カウンセリングを行う現場においては、そうした過去の体験談を知る機会が少なくない。
動画ページ【定期セミナー講演】「アレキシサイミアを基盤に持つコミュ障の症例~深夜にSMSを何度も送りつけてくる理由~」①~③全43分
概要 最初のうちは、予約のやり取りをしていただけのSMS(ショートメール)。ところが、ある日突然そこに「うつになりました」「私は双極性障害です」というコメントが…。そして脈絡のない送信が昼夜問わず何度も来るようになり… […]
動画ページ【定期セミナー講演】「アレキシサイミアとTAS-20の整合性〜実際の診察場面を振り返りつつ〜」①~②全40分
問診の結果を踏まえてTAS-20を実施したところ80点という高得点。痛みの臨床においてアレキシサイミア(失感情症)は治療家泣かせ。心身統合療法士にとっても最重要テーマのひとつ。精緻な問診を進めるなかでアレキシサイミアの可能性を感じ、徐々に核心に迫るプロセス(実際の診察場面)を収録。
動画ページ【定期セミナー講演】「四十肩症例に隠れていたブラインド・マインド」全20分
心理的なアプローチ(軽〜くソフトに内面の話題に触れただけ)に対して異常なほどの反発を示すケースがあります。もしそうした症例に遭遇したら、何よりも真っ先にブラインド・マインドを疑う必要があります。こちらの記事(アレキシサイミアとブラインド・マインドの違い)、こちらの動画(アレキシサイミア)と合わせて、本動画を見ていただければ、あなたの臨床力が200%UPすることをお約束いたします。
動画ページ【定期セミナー講演】「5歳児の医原性CRPS(RSD)の臨床像(父親がグーグル症候群/母親が発達個性/本人はギフテッド)」①~②全35分
染色体異常や運動過剰のない健康体の園児に対して、ゴミ箱診断の極みとも言える、疲労骨折という通常あり得ないラベリングを施すことで患者をCRPS(RSD)にさせてしまった。
アレキシサイミアとブラインド・マインド(盲心)の違い
アレキシサイミアは主に心療内科や精神科の領域で扱われる概念ですが、実は痛みの原因診断において欠かせない非常に重要な視座となります。当会による造語であるブラインド・マインド(盲心)は、何らかの理由(その多くは過去に体験したトラウマからの逃避)により、意識的あるいは無意識的に自身の心を見ない、あるいは見れない患者の心理を指しています。
動画ページ【抑うつ症例に対する認知科学統合アプローチ(COSIA)~リアル診察場面~】英語字幕版あり
概要 動画を見て頂ければ一目瞭然ですが、ボディワークとカウンセリングの両刀使いだからこそ知り得る世界があり、そこに広がる景色の向こうに認知科学統合療法士の未来を見通すことができると思います。 動画内では、施術前後の自 […]
コロナ禍マスク二ケーションの認知科学
マスクによる脳への影響、マスクによるコミュニケーションの問題は日本の未来に深刻な問題を引き起こす。マスクニケーションとは当会による造語で「マスクを介したコミュニケーション」を指す用語。ノンバーバル・コミュニケーション能力が劣化する恐れがあり、後世にわたって社会の在り様を変えてしまう危険性を孕んでいる。
自己相反とアンビバレンスの違い
個人の思いがねじれて脳のエネルギーバランスが崩れると痛み回路が賦活されやすい(→ソフトペイン)。この際の「思いのねじれ」は、感情と理性の葛藤を意味しており、先述したアンビバレンスとは異なる状況。たとえば「本当は…したいけれど、でも…できない(するわけにはいかない、してはならない)」「本当は…したくないけれど、しかし…やらねばならない」のように真の思いと決断のあいだに乖離が生じる状態です。このように真の思い(真情)と思考や論理が相反する状態を自己相反と呼びます。
動画ページ【定期セミナー講演】「麻痺所見と変換症の関係性~整形と精神医学の統合に向けて~」①~③ 全60分
#下垂足 #腓骨神経 #総腓骨神経麻痺 概要 当会はこれまで長きにわたってハード論における神経学的検査の矛盾を指摘してきました。画像所見と神経学的所見が完全に符合する症例は極めて少ないという事実関係は、多くの現場で直 […]
動画ページ【定期セミナー講演】「発達個性の臨床」①~④ 全115分
身体症状症(旧身体表現性障害)や病気不安症(旧心気症)、さらに昔はヒステリーの範疇にあった変換症(旧転換性障害)などが、次元の異なるラベリングをされて通り過ぎている。我々医療者が気づいていないだけで、実際は相当数に上る患者さんたちが…。こうした方々に白衣ラベリングが為されると、本人も医療者も真の病態に気づけないまま事態が遷延化し、治療ベクトルがあらぬ方向に。
動画ページ【生録!傾聴カウンセリングの実際・不登校症例(ネット依存・ゲーム障害・HSC&発達個性)】①~② 全37分
あなたの気持ちを尊重しますよという態度を明確にしつつ、本人の思いに寄り添う傾聴テクニック。大学病院の診断「境界例」に反し、当方の見解は「HSC&発達障害」。HSCはHSPタイプの子供を意味します。本当に今という時代、子供たちの発達はある一面において早熟で、また別の一面では未塾という相反する状態が併存している。障害ではなく、個性として捉えるべき…、なので私は発達障害という言葉は使いません。“発達個性”という概念が大事なんです。
動画ページ【生録!傾聴カウンセリングの実際・寝たきり腰痛重症例(HSP)】①~② 全40分
いかなる物理的介入にも反応しない難治性疼痛に対して、傾聴カウンセリングのみで完治させた実録場面を収録。1年近いタイムラグを経て、「父との死別に対する深い悲しみ」という無意識にくすぶっていたマグマを腰部の激痛発作という形で噴火させていたことを本人に自覚させていく過程がリアルに映し出されている。事実上のグリーフケアを兼ねることになった数十時間に及ぶセッションの、ほんの一部ではあるが、患者が感情解放するリアルなシーンを観ることができる。
動画ページ【定期セミナー講演】「HSP&エンパスの臨床」①~⑨ 全108分
前半ではHSPの基本的なバックグランドを解説し、HSP書籍やエンパス書籍に掲載されている簡易診断テストを会場の全員で実施し、参加者自身のHSPレベル、エンパスレベルを確認。後半において正のラベリングすなわちトップダウン回路の驚くべき力について紹介。是非ご視聴ください。